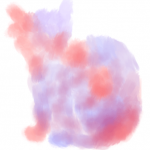徳岡 神泉(1896-1972)
絹本彩色
東京国立近代美術館
神泉26歳のときの作品です。徳岡神泉と言えば、茫漠とした輪郭から精神性のみが浮かび上がってくるような幽玄的な画風を思い浮かべますが、若い頃にはこういう細密画なども描いていたようです。
手元にある画集を見ると20代前半までは、「海老」(1911)、「筒井筒」(1917)、「魚市場」(1918)など、それまで日本画の主流であった花鳥画や歴史風俗を題材にした絵を描いています。しかし神泉はここで行き詰まって描けなくなり、生まれ故郷の京都から逃れるようにして富士山麓の静岡県に移り、ここで4年を過ごしたのだそうです。
その当時の作品を見比べると、京都時代の前述3点と静岡県に移ってからの作品(「狂女(白痴の女)」(1919)、「椿」(1922)など)との間には作風にかなりの隔たりがあります。自分は何を描きたいのか、神泉は悶々として苦しんだ末に、目に映る色鮮やかな現実世界を捨て、その背後に感じる内面世界を描くことを選び取ったように感じます。
この作品からはまだ、後期作品の特徴である象徴的な画風は見受けられませんが、もやの中にたたずむように描かれた椿の姿からは、草花の美しさや情緒はあまり感じられず、その存在そのもの、もしくはその存在から想起される何かを描こうとしたように感じるのです。