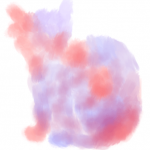ポール・セザンヌ (1839-1906)
油彩・キャンバス
アーティゾン美術館
セザンヌと言うと、林檎でもなくサントヴィクトワール山でもなく、真っ先にこの自画像が目に浮かびます。
塗り残しもかまわず、頻繁に色を変えてがさがさと粗雑に塗ったように見える背景が印象的です。
頭部、特に顔のあたりは色も含めて写実的に描かれているのに、それ以外は何でこんなに雑なのか。特に左下の部分の塗り残しは何か意味があるのだろうか。未完成=可能性を秘めている、ということを印象付けたいのだろうか、とも感じます。
この塗り残しの意味が気になってネットで調べてみました。ブログなどでは見当たらなかったのですが、批評家の洲之内徹が「セザンヌの塗り残し」というエッセーを書いているようなので、さっそく取り寄せて読んでみました。
「セザンヌの画面の塗り残しは、あれはいろいろと理屈をつけてむつかしく考えられているけれども、ほんとうは、セザンヌが、そこをどうしたらいいかわからなくて、塗らないままで残しておいたのではないか」
「凡庸な絵かきというものは、批評家も同じだが、辻褄を合わせることだけに気を取られていて、辻褄を合わせようとして嘘をつく。それをしなかった、というよりもできなかったということが、セザンヌの非凡の最小限の証明なんだ。」(新潮社 セザンヌの塗り残し 気まぐれ美術館 より)
「いつも口から出まかせに思いつきを喋っては忘れてしまう」と自戒しながらもこのように言っています。
ちなみに上記は絶版になっており、古本屋で探して買うか、新刊セット(6冊セットで22,000円 (゚Д゚;) )を買うかですが、見つけたらこの部分だけでも立ち読みしてみても良いかもしれません。まだ読了していませんが、一冊まるごと美術の話題ではなく、大半は昭和初期の世相の雑感がメインのようです。